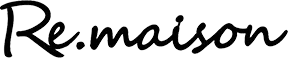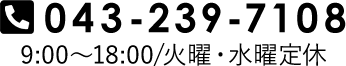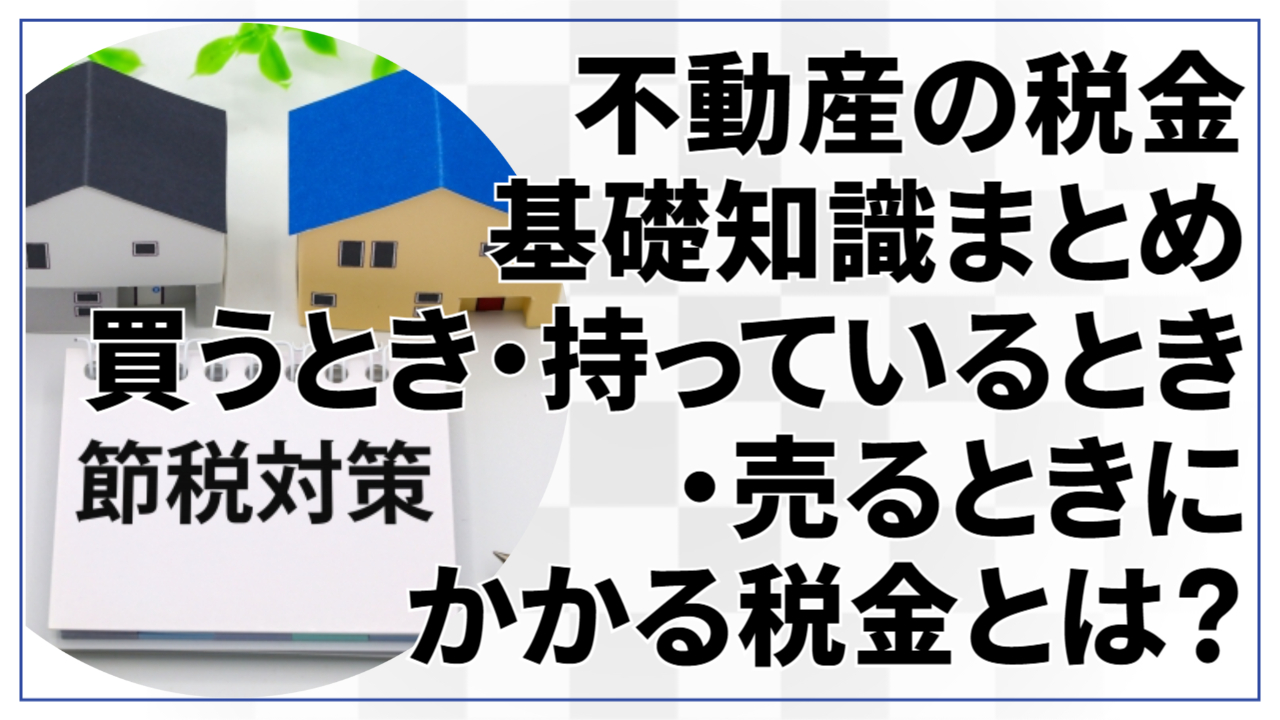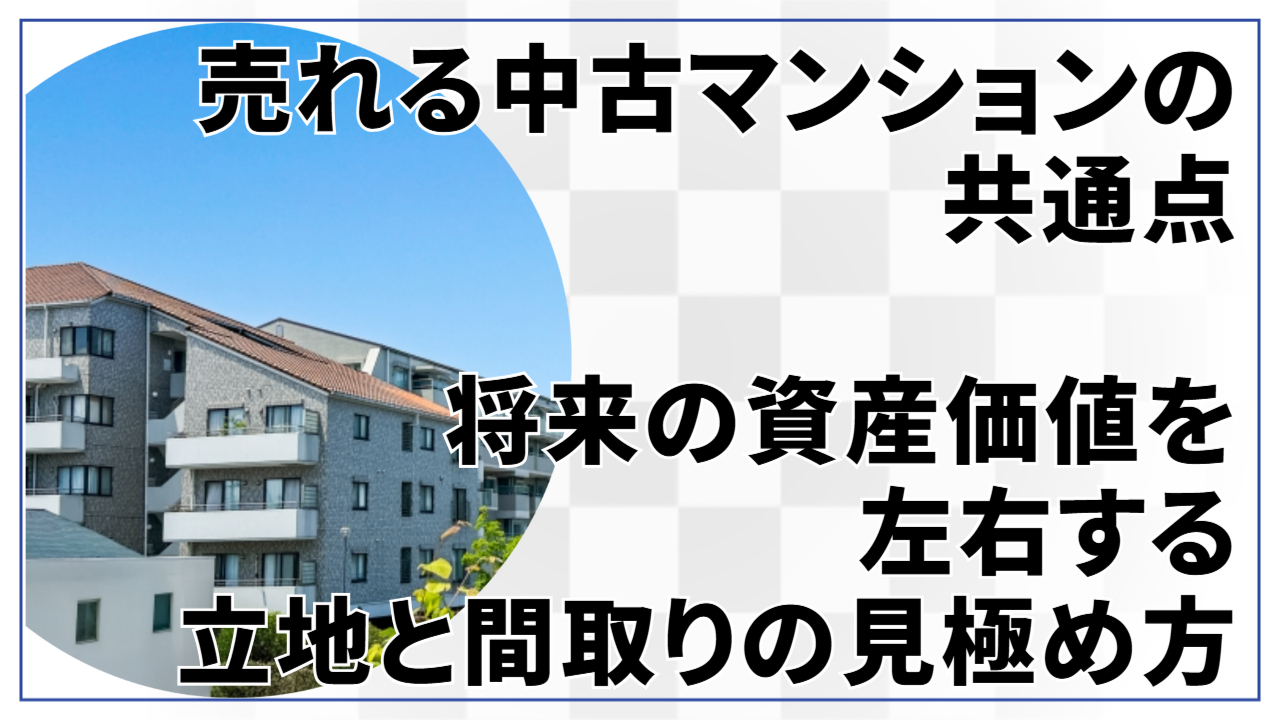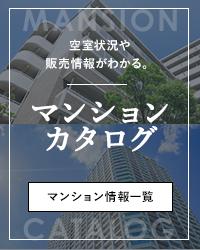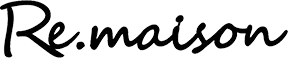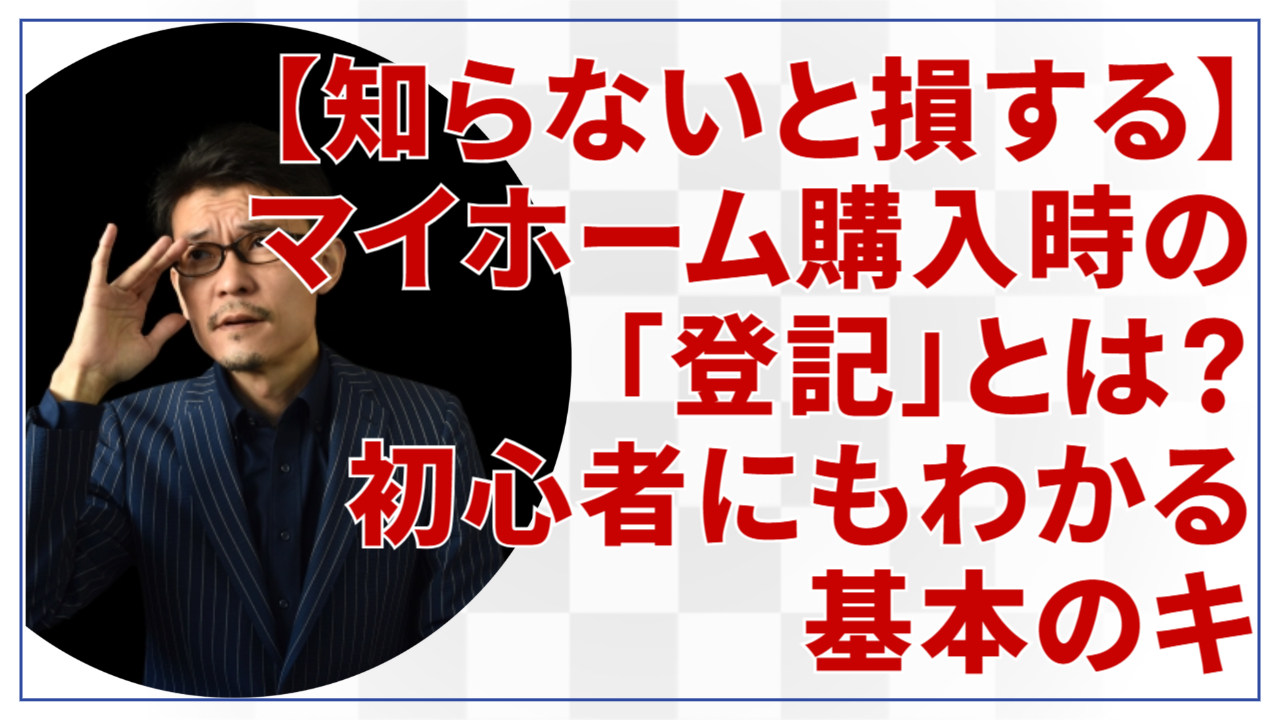
こんにちは。Re・maisonの梅田です。マイホームを購入する際、「登記(とうき)」という言葉を聞いたことがある方も多いかと思います。ですが、「なんとなく不動産屋さんや司法書士に任せてしまって、よくわかっていない…」という方も少なくありません。
今回は、マイホーム購入時に避けて通れない「登記」について、初心者の方にもわかりやすく解説していきます。しっかり理解しておくことで、余計なトラブルや無駄な出費を防ぐことができますよ!
1.登記とは?マイホームの「名義」を証明する制度
登記とは、あなたが購入した不動産(家や土地)の情報を、法務局に正式に登録することです。 これはつまり、「この不動産は誰のものなのか?」を公的に証明する仕組み。
法律上、「登記された名義人=その家の持ち主」となります。 つまり、売買契約を交わしてお金を払っても、登記をしなければ名義は変わらないのです。
これがどれだけ重要か、お分かりいただけると思います。 また、登記の重要性を理解するうえで知っておきたいのが、先日ドラマでも話題になった「地面師(じめんし)」と呼ばれる不動産詐欺の存在です。
地面師とは、他人の土地を自分のものと偽って売買し、詐欺を働く犯罪者のこと。
もし登記が適切に行われておらず、名義や権利関係が不明確な状態だと、こうした詐欺に巻き込まれるリスクが高まります。実際に数億円規模の詐欺事件も過去に起こっており、法務局の登記情報がいかに大切かがわかります。つまり、「登記=自分の権利を守る最後の砦」でもあるのです。

2.どんな登記が必要になる?ケース別に整理
① 所有権保存登記(新築住宅の場合) 新築の建物を初めて登記簿に記載する時に行う登記です。
→ 建物完成後、まだ誰の名義にもなっていない状態から、購入者の名義にする手続きです。
また、新築戸建ての場合は「表題(表示)登記」も必要です。 これは、建物が完成した後に、その構造や床面積などの情報を法務局に登録する手続きで、所有権保存登記の前に行います。通常、表題登記は土地家屋調査士が行うことが多く、これにより登記簿上に建物の存在が明記されます。
② 所有権移転登記(中古住宅の場合) すでに登記されている家を他人から購入した場合、その名義を変更する手続きです。
→ 売主から買主へ、名義を移す登記です。
③ 抵当権設定登記(住宅ローンを利用する場合) 金融機関から住宅ローンを借りる際、物件に「抵当権」を設定する登記です。
→ 返済できなくなったとき、銀行が物件を差し押さえできる権利を登記簿上に記載します。
3.登記にかかる費用とは?
登記をするには費用がかかります。主に以下の2つです。
・登録免許税 登記の手続きを法務局に依頼する際に必要な「税金」です。
【例】
●所有権移転登記:固定資産税評価額の2%(※軽減措置がある場合は0.3~0.6%まで下がるケースも)
●抵当権設定登記:借入額の0.4%(※軽減措置が適用されると0.1%になることも)
●所有権保存登記:固定資産税評価額の0.4%(新築住宅で新耐震基準を満たす場合、0.15%まで軽減されることがあります)
※築年数が新耐震基準(昭和56年6月1日以降)を満たしていると、登録免許税の軽減が受けられます。
・司法書士報酬 登記は専門知識が必要なため、ほとんどの場合、司法書士に依頼します。その際に発生する報酬がこれにあたります。 【相場】 5万~10万円程度(登記内容によって変動)
・登記費用の総額(あくまで目安) 新築戸建て:50万円前後 中古戸建て:30~40万円前後 中古マンション:20~40万円前後 ※注意点として、あくまで一般的な目安であり、物件の価格や評価額、登記の種類によって費用は前後します。